![]()
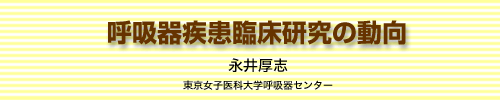
| はじめに
呼吸器疾患の薬物治療に関しては,急性感染症におけるインフルエンザの治療薬の出現や,慢性炎症性疾患である気管支喘息,慢性閉塞性肺疾患,肺線維症などの新規薬物による治療法に新しい展開がみられる。腫瘍性疾患の代表である肺癌に関しては,臨床試験の段階ではあるが,分子標的治療が注目されている。上記に挙げた疾患は,いずれも難治性であり日常診療での維持管理に多くの努力がはらわれているが,満足すべき成果が得られていないのが実状であろう。本稿では,この数年に発表された臨床試験を中心にして,今日,ならびに将来の治療動向につき解説をする。 気管支喘息の日常管理治療の基本は,諸外国や本邦で上梓された喘息予防・管理ガイドラインにみることができる。これらでは,気道攣縮による発作に対してはβ刺激薬の吸入であり,アレルギー性気道炎症に対してはステロイド薬の吸入療法である。喘息の重症度にしたがって一定の基準を目安としながら,実際の診療現場では薬物の種類と使用量を決定するといった手順を採ることになる。しかし,このなかで,テオフィリン製剤や抗アレルギー薬はガイドラインによって取り扱いが大きく異なっている。また,従来より長期にわたる喘息治療のなかでさまざまな議論がなされてきたβ刺激薬に関しては,連続使用により喘息増悪の頻度が増すような成績(図1)1)がみられる一方で,喘息症状の改善にはβ刺激薬の連用が良いとする報告もみられる2)。
抗アレルギー薬として位置づけられている薬種のなかで,今日その効果が臨床のうえから明らかにみられることが確認されているのはロイコトリエン受容体拮抗薬であろう3〜8)。ロイコトリエンは喘息の炎症,リモデリング,発作などをもたらす最も重要なメディエーターである。ロイコトリエン拮抗薬の登場によりその臨床的効果が注目されていたが,現時点での治療成績から考えられる知見をまとめると(1)ロイコトリエン拮抗薬は抗喘息薬として有効(表1,図2),(2)一部の患者ではロイコトリエン拮抗薬に抵抗性であり,その原因としての遺伝子多型,(3)ロイコトリエン拮抗薬はステロイドによって影響を受けず,気道閉塞に関してステロイドとの併用により相加効果(上乗せ効果)があるとするなどの点である。今日,本邦で使用することが可能な薬剤は,pranlukast(オノン),zafirlukast(アコレート),montelukast(シングレア,キプレス)の三種である。pranlukastとzafirlukastが1日2回の服用となっているのに比し,montelukastは1日1回の服用である。基本的には,喘息の日常管理に用いられるが,ロイコトリエンが平滑筋の収縮作用を示すことから,拮抗薬を急性発作の際に静注することによって気管支拡張効果をもたらすことについて検討もされている。
キサンチン製剤は本邦では広く繁用されている薬剤である。しかし,欧米諸国では,安全域の狭いことから毒性が心配され,さらに気管支拡張効果がさほど強力ではないといった点から,治療薬としてガイドラインのうえでもさほど推奨されていなかった。キサンチンはphosphodiesterase(PDE)に対して広範囲な阻害作用を示す薬剤である。PDEはcyclic AMPやcyclic GMPなどの細胞内セカンドメッセンジャーのレベルを変化させることにより細胞機能を調節している。喘息や慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease : COPD)などの慢性炎症性疾患における炎症細胞にはこのなかのPDE4が特異的に多く発現していることが知られるようになった。これらの研究結果や薬理作用のうえから,より選択的に効果を示す抗喘息薬あるいはCOPD治療薬として期待のできるPDE4阻害薬が開発され,現在,臨床試験がなされつつある9〜11)。その安全性と有用性についてはこれらの結果を待たなければならない。 2. 間質性肺炎 間質性肺炎は,肺の間質に主たる炎症性変化が生じ,その結果として肺に広範囲な線維化性病変が形成され,進展すれば呼吸不全に陥る予後不良な疾患である。抗炎症薬としてステロイドや免疫抑制薬を使用するが,疾患の進展や急性増悪時での確実な効果は期待できず,長期間にわたる維持療法としてはその副作用が大きな問題となっている。 近年,新たな薬物療法が試みられているが,そのなかでinterferonγ-1bを長期に使用することにより本症患者の機能的改善が得られたとの報告がなされ12),治療薬としての期待が高まった。しかし,その後の追跡調査により,interferonγ-1bには報告されたような効果はないとの修正見解がなされた。pirfenidoneは抗炎症薬として開発された薬剤であるが,動物実験の経過中に抗線維化作用のあることが見出された。先行する米国での臨床試験では,高度の線維症患者の生存率(図3)や呼吸機能の維持に寄与することが期待される成績が得られている13〜15)。現在,本邦においても治験が進行中でありその結果が待たれる。
3. インフルエンザ 広義のかぜ症候群のなかでも,インフルエンザは全身症状で突然発症し,時に肺炎にまで進展し重症化した例では死に至ることもあり,流行期には十分な注意を要する呼吸器感染症である。インフルエンザに対して65歳以上の高齢者では,感染予防としてワクチンの予防接種が推奨されている。インフルエンザ感染が疑われた場合にはoptical immunoassay法による迅速診断を行うことが可能となった。このような状況下で,近年開発された抗ウイルス作用をもつノイラミニダーゼ阻害薬(リレンザ,タミフル)の吸入や服用によって病気の進展を阻止することが可能となった(表2)。本系統の薬剤は,治療のみならず予防効果もあることが指摘されている。例年,死亡者を出しているインフルエンザに対して画期的な新薬として広く使用されつつある。
4. 肺癌 肺癌は癌死の原因疾患のなかで最上位を占めており,その対策が求められている疾患である。薬物治療に関しては化学療法に若干の進歩はみられるものの,予後に対しての効果はさほど向上していないのが現状である。近年,分子標的治療ともされるチロシンキナーゼ阻害薬が非小細胞癌に対して奏効するとの報告がみられる16〜18)。現在,臨床試験が行われているが,抗腫瘍効果があり副作用も少ないなどの点から延命効果を期待しうる薬剤として有用との指摘がある。 おわりに 呼吸器疾患領域では,病態機序の解明が進むにしたがって問題となる異常に焦点をしぼった標的治療ともいうべき薬剤の開発と臨床応用がなされつつある。本稿で採り上げた薬剤は,いずれもかかる延長線上にあるもので,これまでに治療の糸口がつかめなかった疾患に対して明らかな改善効果を期待することができる。十分な検討がなされていない段階のため結論めいたことは述べられないが,日常的に使用されることによりそれらがいかなる地位を占める薬剤となるか,また,その薬剤効果によって疾患病態の機序が明らかとなる日は遠くないと思われる。 |