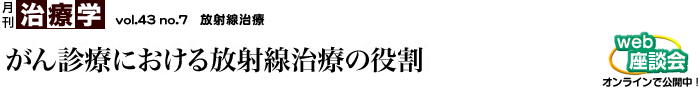
中川 がん治療の 3 本柱は手術,放射線治療,薬物治療で,固形癌を完治できる手段は基本的に手術と放射線治療の 2 つです。 これまで放射線治療は,ある面では外科とのライバル関係で発展してきたと言えるかもしれません。
また,日本は先進国のなかでも放射線治療を「最も」と言ってよいくらいに重視してきませんでした。 放射線治療を受けた患者は,統計のない日本ではがん患者の約 25%と推定されていますが,正確な統計がある欧米では米国で 66%,EU(欧州)で 60%を占めています。
このわが国の背景として,胃癌が非常に多かったことがあげられます。胃癌治療は手術が中心なので,「がん治療=外科手術」という図式ができあがりました。 ただ現在,生活習慣の欧米化により欧米型のがんの罹患率が上昇し,男性は前立腺癌,女性は乳癌が最多になっています。 急速に欧米型になったにもかかわらず,がん治療は手術といった考え方がいまだ維持されています。
甲斐崎祥一先生,外科医のお立場から,放射線治療についてお聞きしたいと思います。
甲斐崎 がん治療として手術だけが認知されてきた理由のひとつは,欧米と比較して日本の手術成績が良好だったことがあげられます。 わが国の外科医が,系統的リンパ節郭清を始めて 50 年以上経過し,今では外国の外科医にはまねのできない“アート”の水準に達していると言ってよいと思います。 その結果,わが国の手術単独の成績は,欧米より 5 年生存率で 10〜20%も良好になっています。
逆に,放射線治療が一般的にならなかった理由は,放射線科医が多くなかったからだと考えています。 大学を離れると,多くの医療機関に放射線科医,特に治療医がいませんから,放射線治療の効果を知る機会がなかったと言えます。 そのうえ,実際に放射線治療を受けた後に外科を受診する患者はすべて,合併症をもっています。
中川 ご自身で手術をなさらなかった患者も,放射線治療後に相談に来られるのですか。
甲斐崎 ええ。放射線治療を受けた患者が外科に来るとしたら,照射の合併症で穿孔したり瘻孔を生じたりした人ばかりです。 しかし,実際には,放射線治療を受けて治癒した人も多数いらっしゃると思います。外科医は,そういう人を診るチャンスがないので,放射線治療に対してネガティブな印象をもってしまうのです。
一方,放射線科医の側でも,「外科が大手術をしたのに,間もなく再発した。こんなひどい状況にして……」という患者しか診ていないように思います。 実際には手術で元気になったがん患者は多数おられます。診療科の壁があって,互いにネガティブにみてきたという経緯があるのではないでしょうか。
今後は,外科手術 vs 放射線治療ではなく,with,つまり併用ですね。この転換に大きく貢献したのは乳癌です。 現在,乳癌手術は乳房温存手術が主流になっていますが,これは術後の放射線照射が乳房内再発を制御してくれてはじめて可能になったと言ってよいでしょう。 現在,直腸癌や食道癌などでも,併用療法が徐々に広がっています。うまく組み合わせて,より質の高い治療ができるようになればよいと思っています。
中川 宮川清先生,いかがでしょうか。
宮川 現在,放射線治療では物理学的に局所に正確に照射することとともに, 内科的な観点,すなわち薬物治療と,いかにうまく組み合わせていけるかが重要な課題になってきています。
そのための臨床試験については,日本では種々の領域で推進されるようになりつつありますが, 放射線治療に関する試験もより活発になることが期待されます。そうなれば,放射線治療の重要性を若い世代にもきちんと伝えられますし, 治療に興味をもって参画してくれる人が増加するのではないでしょうか。
中川 江口研二先生,腫瘍内科のお立場からいかがでしょうか。
江口 私自身も医学部卒業後の 2 年間は放射線科で診断と治療を研修しました。 当時と比較すると,現在の放射線治療は,薬物治療との組み合わせで,根治的治療あるいは症状緩和医療が大きく進歩しました。
腫瘍内科医にとって,放射線治療は非常に重要です。放射線治療は,外科手術と同様に局所療法になり,薬物治療は全身療法であるとされています。 局所と全身のベストな組み合わせ治療が重要で,副作用や後遺症のリスクを最少にし,効果を最大に上げるという意味で,放射線治療は集学的治療として不可欠です。
乳癌・肺癌・直腸癌・食道癌などでは,進行度にもよりますが,手術・放射線治療・薬物療法を併用して,成績がかなり良くなってきました。 根治的な意味をもつ放射線治療の領域は,線質や照射法の進歩でさらに増大すると思います。
中川 緩和医療の手段のひとつとしては,いかがでしょうか。
江口 症状緩和という意味で,放射線治療は骨転移による痛みなどに対して非常に有効です。 より侵襲の少ない緩和的な治療法として,期待しています。
中川 食道癌治療では,放射線治療の成績は手術に及びませんでした。 ところが,放射線治療と抗がん剤を併用すると,効果は手術に肉薄してきました。 まだ十分なエビデンスがないので,現状では手術があくまでも標準治療の第一番になっています。少々問題だと思っています。
宮川 食道癌の診療では,消化器内科医はこれまで診断は担当してきましたが,治療にはあまり関わってきませんでした。 わが国のがん医療における重大な問題は,放射線治療と薬物治療の上手な併用が非常に有効であるという事実を, 多くの内科医が理解していないということだと思います。その解決のためには, 子宮頸癌や膵臓癌など種々の領域における臨床試験のより多くの情報を今後日本からも発信していくことが重要だと思います。 内科医はこれまで,薬物治療だけで治癒が可能な血液疾患や胚細胞腫瘍などは積極的に対応してきましたが, 今後は化学放射線療法の有用性を自ら経験する機会をもってもよいかと思います。 そうなれば,薬物治療を主体にする側から,いろいろな治療のアイデアが出せるのではないかと思うのです。
江口 内科医は内視鏡を用いた診断と診療で活躍してきましたが,薬物療法に関して,十分ではありませんでした。 従来,抗がん剤の種類も少なく手段が限られていたこともありますが,この 10 年で分子標的薬も含めて,各種薬剤の臨床導入が進んでいます。
がん領域では,一流雑誌に報告されるような大規模第 III 相試験はあまり実施されていません。 質の高いエビデンスを集積することが,腫瘍内科や放射線治療分野の問題点となっています。
中川 これまで日本の抗がん剤治療は,基本的に外科の先生が担ってきたわけですね。
甲斐崎 そうです。特に消化器に関して 9 割以上は外科が処方していました。 東京大学医学部附属病院では,主に大腸癌などに対し内科が処方することもあり,その比率は年々変わってきています。 それは FOLFOX(フォリン酸・フルオロウラシル・オキサリプラチンの 3 剤併用)やベバシズマブ,最近のセツキシマブなどの薬剤が出てきたことが理由です。 さらに新薬が出れば出るほど,がんの種類によってかなり差はあるものの,内科医がやらなければいけない状況が増加することは確実だと思います。
中川 外科医側からすると,ある意味で仕事を移譲しているということになりますね。
甲斐崎 実際には「再発したら,内科の先生,診てくれよ」と言いたい外科医は大勢いると思います。 外科が化学療法から解放される時代になれば,外科医を希望する人は増加すると思います。
中川 放射線治療医も足りないのですが,外科医が今後不足することは間違いないですね。
甲斐崎 はい。外科医の過重労働は,手術ではなく,再発後のケアが原因です。今でもほとんどを外科が行っています。
化学療法について言えば,以前は乳癌も直腸癌も胃癌もすべて,抗がん剤はテガフールとウラシルの合剤(UFT)だけでした。 ある意味で,どんな医師が処方しても変わりなかったのです。現在は,薬物治療専門の先生が副作用をケアしながら処方する必要があると思います。