
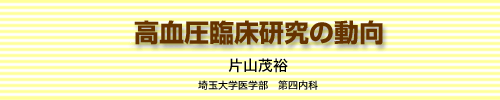
 |
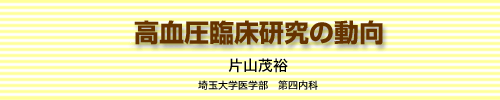 |
|
|
|
はじめに 高血圧患者における利尿薬やβ遮断薬による降圧治療が,脳血管障害や心疾患を減少させることについては,過去30年にわたり多くのエビデンスが積み重ねられてきた。ここ数年の間に,高血圧患者におけるACE阻害薬やCa拮抗薬を用いた大規模介入試験の結果が報告されるようになってきた。また,アンジオテンシンII受容体拮抗薬についても,いくつかのトライアルの結果が報告されるようになってきた。本稿では,これらの成績を中心に,高血圧臨床研究の動向を概観する。 I.続々発表される世界での大規模臨床試験(表1) 1.ACE阻害薬を用いたトライアル ACE阻害薬を用いたトライアルでは,CAPPP(the Captopril Prevention Project(CAPPP)randomised trial)study1)やHOPE study(Heart Out-comes Prevention Evaluation study)2)が挙げられる。HOPEでは,心血管病変をすでにもっていたり糖尿病患者などのハイリスク群でさらに高血圧や高コレステロール血症や低HDL-コレステロール血症や喫煙や微量アルブミン尿を少なくとも一つもっている患者にラミプリルを投与している。ちなみに,糖尿病は約38%に,高血圧は46〜47%にみられた。このような患者群で,ラミプリル投与群ではプラセボ群に比較して,4.5年後に心血管系疾患死・心筋梗塞および脳卒中発症が17.8%から14%に約21%減少した。ACE阻害薬群では,糖尿病関連合併症がプラセボ群の7.6%に比較し6.4%に減少した。最近,3,577人の糖尿病患者だけのsubanalysisの結果(MICRO-HOPE substudy)も報告された3)。これらの患者は,高血圧を約56%に,高コレステロール血症を65%に,心筋梗塞の既往を60%に,脳卒中の既往を7%に,閉塞性動脈硬化症を18%に有するハイリスクの患者である。ACE阻害薬群では,心血管系疾患死・心筋梗塞および脳卒中発症が25%減少した。 最近,Blood Pressure Lowering Treatment (BPLT)Trialists' Collaborationからmeta-analysisの結果が報告された4)。プラセボ(n=6,064)と比較すると,ACE阻害薬による治療群(n=6,060)では,脳卒中が30%,冠動脈疾患が20%,主要な心血管疾患イベントが21%,心血管死が26%,全死亡が16%減少した。有意ではないものの,心不全は16%減少した。ただ,この結果は,多くの症例を先に述べたHOPEに依存している。
2. Ca拮抗薬を用いたトライアルとCa拮抗薬論争 Ca拮抗薬の脳・心疾患発症率に及ぼす影響については,最近ようやく報告されるようになってきた。1998年に,Hypertension Optimal Treatment (HOT)Studyの結果が報告された5)。約19,000人の拡張期血圧が100〜115 mmHgの本態性高血圧患者に,目標拡張期血圧を85〜90,80〜85,80 mmHg未満に定めて,Ca拮抗薬のフェロジピンを主とした降圧治療を行った。3群で最終的な血圧が近接したため,図1に示すように全体では主要な心血管系疾患の発症率に差はでなかった。しかしながら,到達した血圧で再解析した結果,脳・心疾患の発症率は血圧の低いほど低下し,血圧が139/83 mmHgで最低となった。この傾向は,糖尿病患者(1,501人)でより明らかであり,80 mmHg未満を降圧目標とした群の心血管系疾患の発症率は,85〜90 mmHgの群に比べて約50%に低下した(図1)。ただ,全員(92%は非糖尿病患者)での脳・心疾患の発症率に比べると,糖尿病患者の心血管系疾患の発症率は非常に高く,80 mmHg未満を降圧目標とした群のそれもなお28%も高いことには留意すべきである。 60歳以上の高齢者収縮期高血圧を対象としたニトレンジピンを用いたSyst-Eur6)では,2年間(1〜97ヵ月)の観察が行われ,致死的・非致死的を含めた脳卒中が42%減少し(p=0.003),心筋梗塞は有意ではないものの30%減少し(p=0.12),心事故も26%減少した(p=0.03)。 ところで,数年前に即効型Ca拮抗薬が心疾患による死亡を増加させるとPsatyらが報告した。最近,同じグループから長時間作用型Ca拮抗薬を使った試験のmeta-analysisが報告された7) 。Ca拮抗薬は他の降圧薬と比較して,心筋梗塞を1.26倍に,心不全を1.25倍に,主要な心血管イベントを1.1倍に増加させるとの結果であった。しかしながら,Lancet誌の同じ号に,先に挙げたBPLT 4)が掲載されており,Ca拮抗薬による降圧治療(n=2,815)により,プラセボ(n=2,705)と比較して,脳卒中が39%,主要な心血管疾患イベントが28%,心血管死が28%,有意に減少した。有意ではないものの,冠動脈疾患が21%,心不全は28%,全死亡が23%減少した。この結果は,主にSyst-Eurによるところが大であるが,PahorらによるCa拮抗薬論争に疑問符を投げかけるものである。
3. ACE阻害薬 対 利尿薬あるいはβ遮断薬 糖尿病患者を約10%含む高血圧患者を対象として,利尿薬やβ遮断薬という従来の降圧薬と,ACE阻害薬あるいはCa拮抗薬という新しい降圧薬とを比較したStop Hypertension-2 9)では,ACE阻害薬は,利尿薬やβ遮断薬と心血管系疾患の減少に関して同等の有効性を示した。 BPLTのmeta-analysisでは,ACE阻害薬と利尿薬あるいはβ遮断薬で治療した群との比較も行っている。 利尿薬あるいはβ遮断薬(n=2,571)と比較すると,ACE阻害薬による治療群(n=2,605)では,脳卒中・冠動脈疾患・心不全・主要な心血管疾患イベント・心血管死・全死亡ともに,有意差はみられなかった(図2)。 ACE阻害薬は,小規模なトライアルにおいて心筋梗塞後や心機能の低下した患者における心筋梗塞の再発や心不全による死亡や入院のリスクを減少させることが報告されている。また,大規模なものはないものの,糖尿病性腎症における有用性も確立している。しかしながら,脳卒中や心疾患に対する大規模なエビデンスが長らくなかったACE阻害薬の有効性がほぼ出そろったといえる。
4. Ca拮抗薬 対 利尿薬あるいはβ遮断薬 70〜84歳の高齢者を対象としたStop Hyperten-sion-2 8)では,Ca拮抗薬は,利尿薬やβ遮断薬と比較して,すべての心血管事故による死亡率は差がなかった。ただ,脳血管障害におけるCa拮抗薬の利尿薬やβ遮断薬と比較した相対危険率が,有意差には至らなかったものの0.88(0.73〜1.06,p=0.16)となったことは特筆に値する。一方,心筋梗塞のそれは1.18(0.95〜1.47,p=0.13)であった。脳血管障害におけるCa拮抗薬の利尿薬やβ遮断薬に対する優位性は,非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬であるジルチアゼムを利尿薬やβ遮断薬と比較したNORDIL(Nordic Diltiazem)studyでも示された9)。ジルチアゼムの利尿薬やβ遮断薬に対する相対危険率は0.80であった。 Ca拮抗薬のニフェジピンGITSを用いて利尿薬と比較したINSIGHT(Intervention as a Goal in Hyper-tension Treatment)では,致死的あるいは非致死的脳・心血管事故や心不全では両群で差がなかった10)。しかしながら,Ca拮抗薬における致死的心筋梗塞が利尿薬に対して3.22倍,非致死的心不全が2.20倍に達していた。両トライアルの結果は,心疾患に関してさらに今後の検討が必要なことを示唆している。 BPLTのmeta-analysisでは,Ca拮抗薬と利尿薬あるいはβ遮断薬で治療した群との比較も行っている(図3)。 利尿薬あるいはβ遮断薬(n=11,769)と比較すると,Ca拮抗薬による治療群(n=11,685)では,脳卒中が0.87倍に有意に低下した。冠動脈疾患や心不全は,有意ではないもののそれぞれ1.12倍に増加した。主要な心血管疾患イベント・心血管死・全死亡ともに,有意差はみられなかった。このことは,利尿薬あるいはβ遮断に比してCa拮抗薬の脳卒中予防に対する有用性を初めて示した結果といえ,脳卒中の多いわが国にとってその意義は大きいといえる。日本人における大規模トライアルが望まれる。
6. アンジオテンシンII受容体拮抗薬の位置付け わが国でも,アンジオテンシンII受容体拮抗薬の臨床応用が始まり3年になる。その確実な降圧作用や特徴的な副作用がないことなどから,広く受け入れられつつある。心不全患者におけるACE阻害薬のカプトプリルとの同等性はロサルタンを用いたELITE IIで証明された13)。また,ACE阻害薬や利尿薬やジゴキシンやβ遮断薬ですでに治療を受けているNYHA II〜IVの心不全患者にバルサルタンを併用した際に,総死亡を含む心血管イベントが13.3%減少し,心不全による入院が27.5%減少することがVal-HeFT(Valsartan Heart Failure Trial)で証明された(第73回米国心臓病学会)。糖尿病性腎症に対する有効性は,動物実験では報告されている。微量アルブミン尿を認める正常〜高血圧のNIDDM患者にバルサルタンを80 mg あるいは160 mg/日を12ヵ月投与した成績では,アルブミン排泄率は,それぞれ28%(n=27),21%(n=31)減少し,カプトプリルでみられた27%(n=29)の減少と同等であったという14)。ロサルタンやバルサルタンを用いた大規模臨床試験RENAALやABCD-2Vの結果が待たれる。また,ACE阻害薬との併用がおのおの単独よりも有効ではないかとの期待もあり,検証が望まれる。 |