![]()
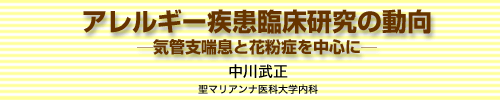
| [1.気管支喘息] |
|
1.気管支喘息
気管支喘息は現在,気道の慢性炎症性疾患として理解されている。すなわち,Th2細胞,好酸球,マスト(肥満)細胞を中心とする炎症細胞と,それから遊離される種々のメディエーターやサイトカインが関与する急性・慢性炎症(アレルギー性炎症)によって病態が形成される1)ことが明らかにされている。したがって今日喘息治療は,この炎症をいかに制御するかを主体として行われており,吸入ステロイド薬や抗アレルギー薬などがこの目的のため汎用されている。なお喘息の急性増悪に対しては,発作治療薬として吸入β2受容体刺激薬やアミノフィリン,経口・静注ステロイド薬などが用いられるが,誌面の関係でここでは触れない。 |
| 1. 吸入ステロイド薬
吸入ステロイド薬(IS)は,気管支喘息の長期管理において中心的役割を果す薬剤である。わが国には1970年代後半に導入されたが,その投与が一般化したのは1993年の喘息治療ガイドラインの公表以降である。その普及にともなって,喘息発作による救急外来受診数や入院数が減少したことは明らかな事実である。わが国では現在,ISとしてベクロメタゾン(beclomethasone dipropionate : BDP)とフルチカゾン(fluticasone propionate : FP)が使用できる。また3番目のISとしてブデソニド(budesonide : BUD)があり,製造承認は出されているので近日中に発売されることであろう。その他代替フロンを用いるBDPや,新規dry powder製剤であるmomethasoneなどが検討されており,将来使用可能となろう。 ISの臨床エビデンスとしては,第1選択薬としての位置付け,早期導入の効果,併用薬による減量効果,減量中止の影響などに関して,inactive placeboなどを対照とした多くの治験報告がある。たとえば軽症喘息例でのISと,各種気管支拡張薬や抗炎症薬であるdisodium cromoglycate(DSCG)との比較試験では,臨床諸指標の改善においてISが有意に優れていることが示されている2〜4)。また症状発現からIS導入までの期間が短いほど患者の肺機能障害の程度が軽く,肺機能の改善率も優れているとの報告も認められる5〜6)。さらにはISが喘息死を減少させるというエビデンスも報告されている7)。そのまとめを昨年公表された“EBMにもとづく喘息治療ガイドライン”8)より抜粋して表1に示すが,詳しくはガイドラインを参照されたい。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 抗アレルギー薬
抗アレルギー薬は,“I型アレルギー反応に関与するメディエーターの遊離ならびに作用を調節する”薬剤であり,「喘息予防・管理ガイドライン1998改訂版」1)では(1)メディエーター遊離抑制薬,(2)ヒスタミンH1拮抗薬,(3)トロンボキサン阻害薬,(4)ロイコトリエン拮抗薬,(5)Th2サイトカイン阻害薬,に分類されている。その一覧を表2として示すが,わが国では2001年9月現在26品目が市販され,臨床の場で汎用されている(喘息を適応とするものは19品目)。
これらの薬剤はinactive placeboやactive controlを対照とした臨床治験にもとづいて認可されたものであるが,その臨床エビデンスに関する英文報告はさほど多くはない。代表的なエビデンスを前述のガイドライン8)より抜粋して表3として示すが,わが国からの報告としてはロイコトリエン(LT)拮抗薬やTh2サイトカイン阻害薬などによるIS減量効果や気道炎症細胞浸潤抑制効果9〜12)がその主体となっている。 なお最近注目されているのが,軽症例でのLT拮抗薬の第1選択薬としての位置付けである。実際にアメリカNIHによるガイドライン(Expert panel report II)ではISにかわりうる選択肢として取り上げられている。両者の比較試験の結果をみると,臨床諸指標の改善効果はISの方がすぐれているが,効果の発現はLT拮抗薬の方が早いとされる3)。またISと併用して減量効果を求めるのに,LT拮抗薬montelukastと長時間作用性β2吸入薬であるsalmeterolのどちらが優れているかのprospective studyが,現在ヨーロッパで行われている(IMPACT study)13)。さらには現在抗アレルギー薬の効果予知が,遺伝子多型の検討や血清・尿中のメディエーター測定などで試みられている。これらが可能になれば,個々の病態に応じた抗アレルギー薬によるテーラーメード医療が実現できる可能性があろう14)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||